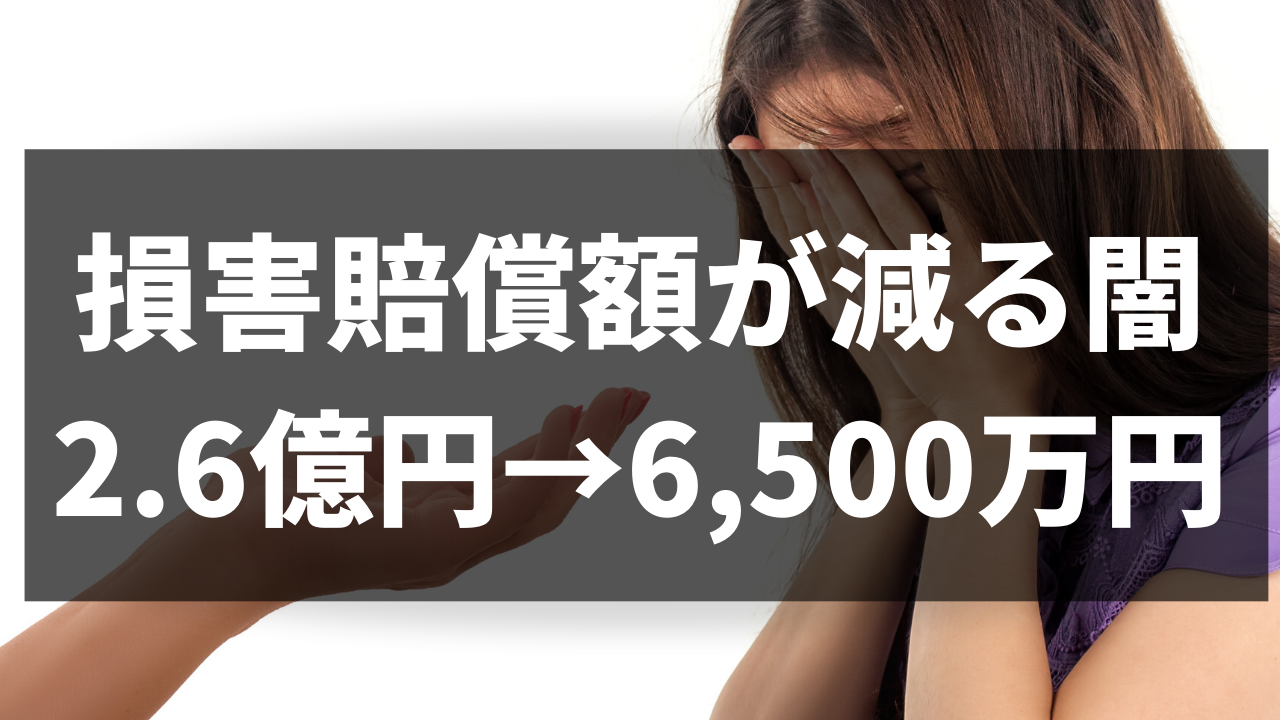HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。
先日、新聞各紙に大きな見出しが。
「最高裁初判断!事故逸失利益 定期払い容認」という記事です。
私の感想は「マジか!」という驚きでした。
個人が保険会社と裁判で闘い、しかも勝つということがいかに難しいか。。
この裁判の話題から、資産形成コンサルタントとして見逃せない内容があったので解説します。
【裁判の詳細】
ググれば詳細が出てきますが、こちらでも紹介させていただきます。
2007年に当時4歳の男児がトラックにはねられました。
男児は入退院を繰り返し、5年余り経っても脳に障害が残りました。
保険調査による障害等級で労働能力の喪失は100%とされ、約2.6億円賠償を求めましたが、一時金では6,500万円になるということで、“定期金”として毎月45万円受け取れるよう提訴しました。
「交通事故の賠償」
交通事故を起こしてしまった場合、任意保険に加入していれば損害保険会社が被害者へ賠償金を支払います。
損害保険とは、実際に発生した損害額までしか補償してくれません。
生命保険はいくらでも自由に保険金を設定できますが、損害保険はそうはいきません。
今回の場合は、トラックにはねられたことによる損害はいくらなのか?ということがポイントです。
治療費はもちろん、被害者が働けなくなった場合は「事故がなかった場合に、将来生み出したであろう利益(収入)」を「逸失利益」として請求できます。
「逸失利益とは?」
もし事故がなかったら将来これだけの利益(収入)を得られたはずというものを「逸失利益」と言います。
死亡や後遺障害も、この考え方は同じです。
“休業損害“とイメージしてもらうと分かりやすいと思います。
逸失利益は
基礎収入額×労働能力喪失率×対象年数の係数
で求められます。
・基礎収入額
原則として事故が起きる前の、実際の収入額を基礎として算出します。
サラリーマンや公務員(給与所得者)は、事故前年の年収額(賞与含む)、事業所得者(経営者等)は事故前年の申告所得額が基準になります。
今回の裁判ではまだ就労前の子供についてです。
被害者が子供の場合は「賃金センサス(統計による平均給与)の男女別全年齢平均賃金」の金額を基礎収入額にします。
・労働能力喪失率
労働能力喪失率は“後遺障害等級別“に決まっています。
障害等級は第1級〜第14級まであり、第3級より重い障害等級になると労働能力喪失率は100%になります。
今回の裁判では、労働能力喪失率は100%とされています。
・対象年数の係数
何歳までを補償しなければならないのか?は目安が決まっています。
基本的には「症状固定から67歳まで」とされています。
被害者の健康状態や能力などによって多少変わってきます。
67歳間近もしくは超えている人は「症状固定時の年齢の平均余命の半分」の年数を労働能力喪失期間とします。
そして、ここからが私が気になったポイントです。
対象年数の係数、係数とは「ライプニッツ係数」というものを用います。
一括で支払う分、それを3%(2020年3月までは5%だった)で運用したら増やせるんだから、その分一括で支払う金額から利息分を差し引くよ。という係数です。
専門用語を使って説明すると、年金現価係数です。(FP試験に出てくる基礎です)
「49年間で総額2.6億円を請求」
今回の裁判では、18歳から67歳まで働いていれば得られたであろう利益(収入)として約2.6億円を求めて提訴しました。
細かい計算は明らかになっていませんが、新聞記事では2.6億円を求めた場合「運用できるから少なくするね」ということで一時金での支払いは6,500万円になるということでした。
「ほぼ100%の被害者が一括払いで受け取る」
交通事故のよる賠償金はほぼ全員が一時金で受け取っているそうです。
理由としては、保険会社と戦い続ける覚悟がないからとのこと。
たしかに、一個人が保険会社を相手取って裁判を起こすことがいかに凄いことか。
定期金で受け取るとなると、その間ずっとその保険会社とやりとりすることになります。
そうなるともちろん、支払いが滞る可能性も考えられます。(保険会社が倒産する可能性も)
こうした理由から、ほぼ全員が一時金を選択しているそうです。
【賠償金の受け取り方】
メリットとデメリットをまとめておきます。
「一時金」
メリット
・まとまった金額を早期に受け取れる
・将来の経済動向は無関係
デメリット
・将来障害状態が重くなっても何も請求できない
・利息が控除されるので、受け取れる金額が大きく減る
「定期金」
メリット
・利息が控除されないため、受け取れる金額が減らない
・障害状態が重くなったら、請求金額を見直せる
デメリット
・保険会社とのやりとりがずっと続く
・支払いが滞る(保険会社倒産)リスクがある
【超低金利時代なのに2.87%運用ってどうやるの?】
「6,500万円を年複利2.87%で運用すると2.6億円になります。」
2.6億円を求めても、一時金での受け取りだと利息を控除されて6,500万円しか受け取れないということはこういうことです。
この超低金利時代に、円建てで、元本保証で、年複利2.87%で運用できる方法って何がありますか?
もしあるのならば、資産形成コンサルタントとして是非とも知りたいものです。
【裁判の結果】
18歳から67歳までの49年間、毎月45万円を支払うよう求めましたが、札幌高裁は毎月35万円を支払うことを命じました。最高裁もこれを認めました。
先述の通り、定期金にはメリットもデメリットもあります。
総額は一時金よりも大きくなりますが、これからが大変そうです。
何より、最高裁が「定期払いもアリ」と認めたことが大きいと思います。
今後は受け取り方について選択肢ができ、被害者にとって悪いことではないです。
保険会社からしたら、支払い総額は増え、被害者とのやりとりが長期に渡り、負担が大きくなると言えます。
保険金支払いシステム見直し人件費の増加が考えられますが、これらは保険加入者の保険料から支出されるので、定期払いを求める被害者が増えれば、保険料が上がるということになりそうです。
【まとめ】
逸失利益や慰謝料を一時金で支払ってもらう場合、利息を差し引いて支払われます。
年数が長ければ長いほど減ります。
その利息に用いられている利率がおかしいと思います。
超低金利時代の今、ライプニッツ係数に用いられている利率は3%です。
(2020年3月以前に起きた事故は5%)
先進国の物価上昇目標よりも高い利回り、かつ円建ての元本保証で運用できる人はどれだけいるのでしょうか?
こうした当たり前を、みんなが疑問に持ち、みんなが声を挙げて変えなければならないと思います。
LINE公式アカウント友達追加で2大特典プレゼント!
虎の巻其の壱「クレジットカード」
年間37万マイル貯める男が使うクレジットカード1枚を大公開!
虎の巻其の弐「ふるさと納税の極意」
ふるさと納税の自己負担が実質0円!?知らなきゃ損の裏ワザ!
その他、セミナー情報をはじめ世界情勢や旬な情報をお届けしています!
YouTubeもやっています!「とらしげ社長のFPチャンネル」