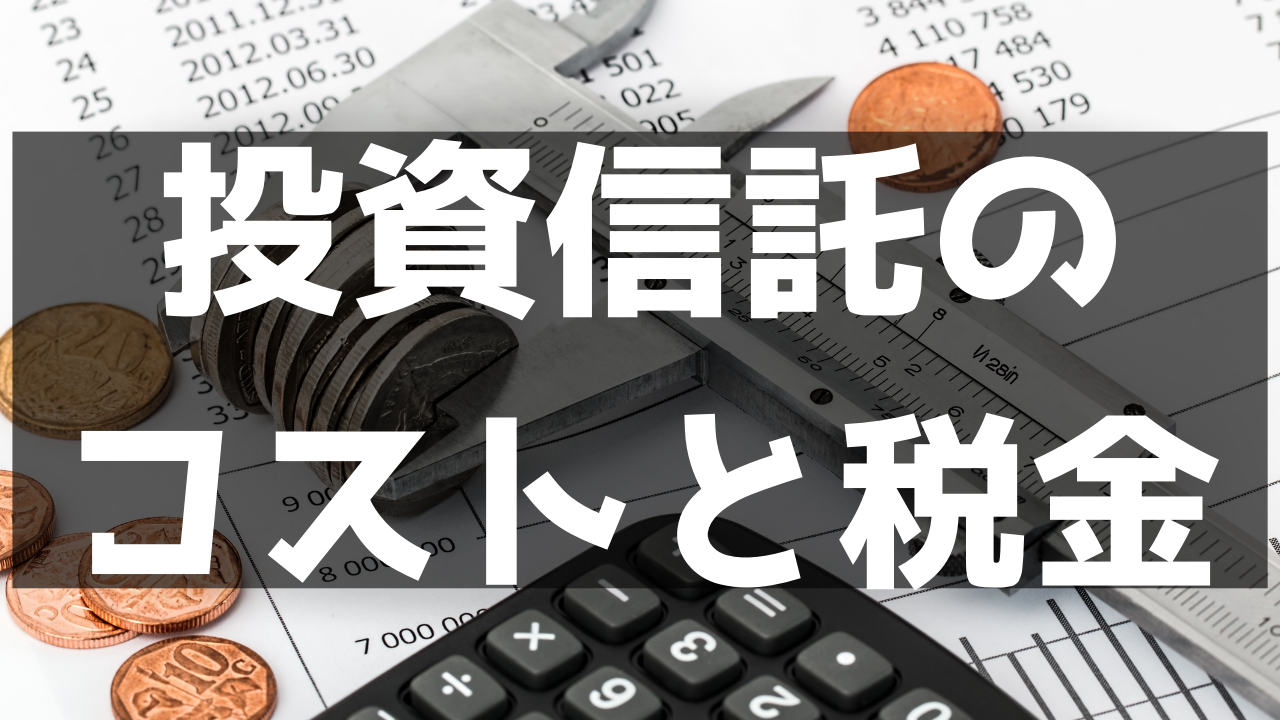HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。
投資信託のデメリットである様々なコスト、これを把握しておかないと運用ではプラスでも、コストを支払うとトータルでマイナスになりかねません。
また、税金の仕組みも知っておかないと余計な手間がかかります。
基礎は大切ですね。どんぶり勘定で始めてはいけません。
【投資信託の税金】
税率は上場株式等・公募株式投資信託ともに20.315%です。利益に対して20.315%ね。
一昔前までは確定申告しないと損益通算(配当金・分配金などのプラスを、譲渡損失などのマイナスとで課税の対象額を減らすこと)できませんでした。
投資家の負担を減らすために、2010年1月からは特定口座(源泉徴収あり)で損益通算できるようになりました。(確定申告不要)
その特定口座とは何か?
【特定口座とは】
種類が「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2つがあります。
とくに事情がない人は「源泉徴収あり」の方がいいです。
「源泉徴収ありの特定口座」
特定口座内の投資信託を損益通算し、利益が出ていれば税金を徴収(源泉徴収)した後、収益が口座に入金されます。
「源泉徴収なしの特定口座」
先ほどの「源泉徴収あり」とは違い、利益が出た場合は投資家が申告する必要があります。
特定口座内にある投資信託などは、損益通算した上で申告に必要な書類を送付してくれます。
そのため、わざわざ個別銘柄の残高証明などを自分で揃えたり、計算する手間はありません。
【投資信託にかかるコスト】
投資信託のデメリットとも言えるコスト。
何に、いつ、いくらかかるのか把握しておきましょう。
運用がプラスでも、コストを考慮しておかないとトータルでマイナスなんてこともありえます。
購入時手数料
「タイミング」
購入時
100万円分の投資信託を購入したい場合、仮に購入時手数料が3%だとすると103万円必要です。
「手数料込み」を選択できる場合は、970,873円分の投資信託と購入時手数料3%(29,126円)で100万円以内に収めることが可能です。
「支払い方法(直接or間接)」
直接
「費用の内容」
投資信託購入時に販売会社に支払う費用です。
申込価額の数パーセントを支払います。
ファンドや販売会社によっては換金時に支払うものもあったり、この費用自体がないものもあります。(費用がかからないものをノーロードという)
運用管理費用(信託報酬)
「タイミング」
保有時
「支払い方法(直接or間接)」
投資信託の信託財産から間接的(自動的)に支払われるので、新たに支払う手間はありません。
「費用の内容」
投資信託を保有している間、保有額に応じて支払う費用です。
目論見書などに詳細(年いくらなのか等)が記載されています。
監査報酬
「タイミング」
保有時
「支払い方法(直接or間接)」
投資信託の信託財産から間接的(自動的)に支払われるので、新たに支払う手間はありません。
「費用の内容」
原則として決算ごとに監査法人などから監査を受ける必要があるので、それに要する費用です。
売買委託手数料
「タイミング」
株式などの売却時
「支払い方法(直接or間接)」
投資信託の信託財産から間接的(自動的)に支払われるので、新たに支払う手間はありません。
「費用の内容」
投資信託に組み込まれている株式などを売買する際に発生する費用です。
発生の都度、間接的に徴収されていますが、事前にいくらかかるのか示すことはできません。(運用次第で都度かかってくるので事前にはわからない)
信託財産留保額
「タイミング」
換金時
「支払い方法(直接or間接)」
直接
「費用の内容」
投資信託を購入または解約する際、手数料とは別に徴収される費用です。
販売会社が受け取るのではなく、そのまま信託財産に留保されます。
投資信託によって差し引かれるものと差し引かれないものがあります。
【まとめ】
いろいろコストがかかりますねえ。
それでもプラスにする自信があるから運営しているのでしょうし、実際に何年も続いている投資信託は結果を出せているということです。
コストが少ないからといって飛びつき、そのコストに対して見込める運用益が少ないともったいないです。
銘柄選定には、目標に合わせた総合的判断が求められます。
「はー、むり」という方はプロの私にご相談ください。