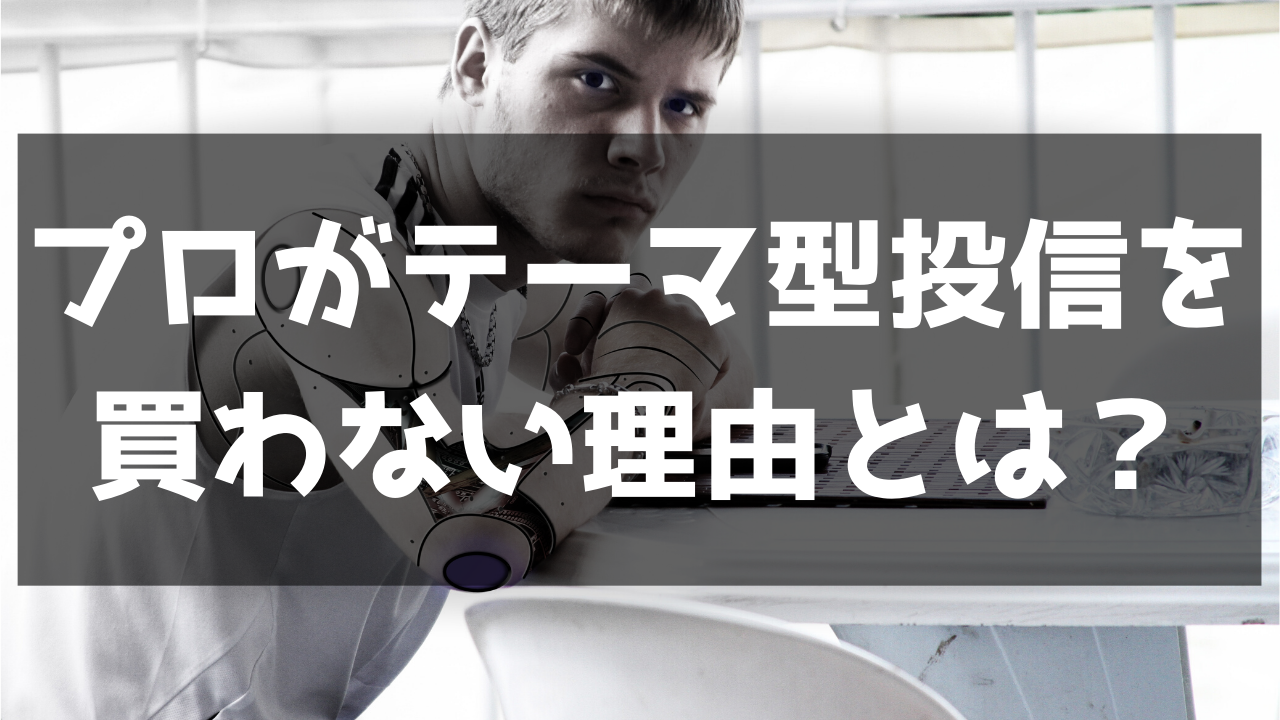HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。
少し知識を身に付けた人が買いがちなのが“テーマ型投資信託”です。
私もおすすめしていません(むしろディスりがちです)
「テーマ型ファンド(投資信託)の罠、割安だと勘違いする理由」
今回はテーマ型投資信託のデメリットを中心に解説していきます。
【テーマ型投資信託(ファンド)とは】
世の中で話題になっている(今後伸びると考えられている)テーマ、たとえば過去の例ではITやバイオなどに関連する銘柄に絞って投資するファンドのことを指します。
とくに初心者に人気なイメージがあります。
その理由として
・営業マンが薦めてくる
・パンフレットが素敵(初心者でもわかりやすい)
・未来を見通している感じがする(投資してる感)
もちろん、好成績のファンドもありますが、最近ではテーマ型から他のファンドへの資金流出がニュースになっていたり、あまり良いイメージがありません。

出典:日本経済新聞投信コラム「2019年の年初から9月末までのデータ」
【プロがテーマ型投資信託を好まない理由】
「手数料が割高」
基本的に、絞ったテーマへの集中投資であり、アクティブ運用型です。
(インデックス型よりアクティブ型の方が手数料が高い)
また、旬な商品なので営業マンが集中して営業活動を行ったり、素敵なパンフレットを作るコストも、投資家が支払う手数料が原資です。
ファンドオブファンド(投資信託に組み入れる金融商品が投資信託の商品)であることが多く、その分手数料は高くなります。
「分散投資されていない」
投資信託の魅力は、1つの投資信託を購入することで様々な金融商品に分散投資できることにあります。
しかし、テーマ型投資信託では、絞られたテーマへの“集中投資”であるため、分散が不十分なことが多いです。
つまり、そのテーマ関連がダメになると一気に損失が拡大する可能性が高いのです。
逆に言うと、そのテーマ関連で好材料が発表される大きなリターンを得られます。
「新規設定だから過去の運用実績がない」
テーマ型の特徴として、販売前から営業マンが“購入する人”を集めます。
集めに集めて、一気にスタートさせ、ランキング上位に表示させ、さらに売れるようにするという手法が一般的です。
海外の機関投資家(プロ)たちはとくに過去の運用実績を重視するので、それがないテーマ型には好んで手を出しません。
日本人は「販売開始前の、未来ある(伸びそうな)銘柄を買えるなんてええなあ」と謎の優越感に浸って購入しがちです。
時代を先取ってる感じがいいんでしょうかねえ。。
実際に私もお客さんから「証券会社に販売開始前の商品(テーマ型)を勧められたけどどうでしょうか?」という相談は多いです。
基本的に当ブログと同じ内容を説明して購入を見送る方向で回答しています。
【まとめ】
テーマ型はハイリスクハイリターンと言えます。
長期投資を目的として購入するものではありません。
プロが買わない主な理由は
・手数料が割高
・分散投資できない
・過去の運用実績がないものが多い
素敵なパンフレットに騙されないようにしてください。
私のような人に相談できると損しないで済みますよ。